

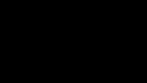
DOCUMENTARY FILM
ONIGAWARA

ドキュメンタリー映画
『鬼瓦』について
日本書紀で記された瓦の歴史や鬼の伝承を紐解きながら「鬼瓦」の姿に迫ります。記録映画を通じて日本の伝統工芸・文化を国内外の方に発信するプロジェクトです。2024年以降劇場公開予定。
This film explores the history of kawara (roof tiles) as recorded in the Nihon Shoki (Chronicles of Japan) and the folklore of ogres. This project is designed to promote traditional Japanese crafts and culture to people in Japan and abroad through documentary films.
昨今、漫画の題材でも鬼に注目が集まっていますが、瓦の世界にもその昔から鬼が存在していました。
⻤⽡は棟端に置く装飾瓦の総称です。鬼の顔を象った瓦が鬼瓦というわけではありません。そして鬼瓦を製作する人々を鬼師と呼びます。一般的には魔除けの存在として考えられ、社寺仏閣の棟の端などに設置されています。鬼瓦の起源は古代ギリシャやエトルリアで使用されていた屋根飾りと繋がりがあるともいわれています。海外の聖堂にもガーゴイルなどが設置されていますが、動物の面や頭部の彫像は古来から魔除けに用いられてきた歴史があるそうです。日本の鬼瓦にもその歴史が受け継がれているのかもしれません。
6世紀頃に仏教とともに伝わっとされる瓦。日本書紀には瓦の導入にあたって朝鮮半島の百済から瓦の技術者「瓦博士」4人が派遣されたとの記載があります。実際に日本で一番最初に建てられたと言われる飛鳥寺では、百済のものとそっくりの瓦が出土されています。日本の歴史・そして宗教とも密接に関わる瓦の存在。しかし初期の鬼瓦は現在のような鬼の姿をしていませんでした。一般的には魔除けの存在として考えられる鬼瓦はどのような経緯で現在の鬼の姿に変移していったのか。鬼瓦を製作する鬼師、研究者の取材をもとに象られる鬼の姿に迫ります。そして日本の鬼の伝承とも向き合いながら、その文化形成の魅力を国内外に向けて映画祭出品、劇場公開、配信を目指し制作を行ないます。


ドキュメンタリー映画「鬼瓦(仮)」
撮影を支えるレンズたち
-映画表現で活きるコシナ製レンズの魅力に迫る-
comment
堤幸彦 (映画監督)
鬼師のまち=高浜市と何本かの市民ムービー作りにかかわりました。人を魅了する鬼瓦、その秘密を知りたくなりました。6世紀頃の渡来人あたりから作り上げられてきた日本の文化史のある側面、また鬼伝説とはなにか。現代の鬼瓦作りを通じてそんな興味への解答がほしい、映画「鬼瓦」期待します!
吉添裕人 (空間デザイナー)
屋根を構成する瓦の中でも重要な役物として鎮座する「鬼瓦」。昔から構造体と構造体の重要な接点を担いながら、静かに私たちを見守ってきました。そんな「鬼瓦」のなんとも言えない魅力。それはモチーフとしての力強さや、歴史が培ってきた建築的な概念や構造にも深く関係していることに疑いはあ�りませんが、その側面だけでは説明できないこの佇まいはどこから生まれてくるのでしょう。古代より現代まで引き継がれてきた様々な「鬼瓦」の歴史、製造技術、それを取り巻く人々の姿は現代においての私たちの暮らしに多くのヒントをもたらしてくれそうです。その秘密の片鱗がこのフィルムによって紐解かれることを楽しみにしています。
首藤勝次 (竹田市 健康と温泉文化・芸術フォーラム理事長)
鬼瓦のパイロット版を見せていただき、すぐに『美術は宗教と等しい』という言葉を思い起こした。人類のあらゆる芸術の源は宗教であるとするものだが、日本美術で最も洗練されたのは仏教美術であり、西洋ではキリスト教と結びついて発展した。さらに、具象的な造形を禁じたイスラムでも建築や装飾に刮目すべき芸術を生み出していることを知れば、日本に伝存する最古の正史とされる日本書紀に鬼瓦の記述があるのは何の不思議もないが、だからこそその伝来や意味を解き明かす作業からは意外な真実が現れるのかも知れないと期待を寄せているところなのである。
赤神諒 (小説家)
小説で、鬼瓦のような顔をした戦国武将をライフワークとして描いています。 「鬼瓦」という言葉だけで、我々は共通のイメージを抱く。 圧倒的な強さと荒々しさ、頼もしさを持つ、不格好だがユーモラスな、聖なる何か。 そこには、神にも似た近寄り難さと、土塊にすぎない人間の切なさが見える気がします。 タカザワカズヒト監督が、本質に迫る切り口と抜群の映像美を武器に、鬼瓦の不可思議な魅力の謎を解き明かしてくれるでしょう。
深田隆之 (映画監督・海に浮かぶ映画館 館長)
私が鬼瓦を見るとき、それはいつも神社仏閣の屋根や大きな家の屋根にある。私は下から遠くにある鬼瓦を見つめるが、鬼瓦はこちらを見向きもせずどこか別の場所を毅然と見つめ続けている。今回のパイロット版を観て、鬼瓦とカメラ、その距離の近さにまず驚くとともに、こちらがカメラを通して睨まれるような圧倒的な視線を感じた。普段体感することのできない鬼瓦の質量、そして丁寧にヘラを入れる職人の手を見るだけで魅了されてしまう。私がいつも見る鬼瓦は厄災の方を見つめ、その建物をじっと守っていたのだろう。この睨みが立ち上がる瞬間、鬼瓦に魂が練り込まれる瞬間を克明に記録してほしい。
松澤斉之 (日本工芸株式会社 代表取締役)
ある種の伝統工芸でもある「鬼瓦」が映画の題材としてどのようなコンテクストを持つのか、非常に興味深かった。視聴者に対し、どの様な描き方でこれまでの歴史の物語を伝えるか、楽しみでなりません。近年は鬼瓦の技術を駆使し家庭でも使用できるプロダクトが増えています。時代と共に変化する伝統工芸の魅力が、映画で表現される事を期待します。


